愛知低山登山開始~石巻山前編

3連休初日は無事山登りの予定も実行し、しかもちゃんと夜のウォーキングまでこなして17000歩以上歩けて遠出はできなかったけど充実した連休をスタートできたと思うまろぱぱです。
残念ながら3連休最終日の月曜日は奥さん仕事に加えシオリはテスト前だし、リョータが業務多忙につき休日出勤になってしまったし、ソースケが部活だと判明したので、完全にどこにも行けなくなってしまいましたが。
一人で何しようかな・・・やっぱりDOOMか!?(爆)
ということで、昨日は予定通り午前中からご近所の低山、石巻山に山登りに行ってきました。
ご近所だけど初めて登る山なので、事前にスマホアプリ「YAMAP/ヤマップ」をインストールして臨みましたが、このアプリ便利ですね~
登山道が記された地形図に現在地が表示されるし、色々注意点も書いてあるし。
山登りに必携アプリですね。
そして10時を回ったらドラッグストアーでアミノ酸入りゼリーと飲み物、そしてスポーツ羊かんに、昼ごはんのカップ麺とおにぎりを購入して出発
事前に調べておいたこちらの駐車場には20分くらいで到着。とっても近いです♪

まあ我が家から見えている山ですからね。
そして靴を履き替えてデイバッグに荷物を詰め込んだら登山開始
ここが登山道入り口

こんな林道を進んで行きます。

最初は勾配が比較的なだらかなので今日は大丈夫そうな奥さん

しばらく森の中を歩くと別登山口からのルートと合流

こういうのもヤマップに記載されているので道間違いが無くなりそうです♪
そしてこの登山道はちゃんと石巻山自然歩道として整備されているので歩きやすいです。

標高を上げていって森が開け明るくなりました。

石巻山自然歩道は続く

これくらいの山道が楽しいな~(^^;)

今のところ豊橋や豊川でクマが出たという情報はないので熊鈴は外しましたが、念のため音楽をスマホで流しながら歩きました。
そして車道と合流。暑くなったので上着を脱ぎます。

登山道はこの車道のすぐ上の石巻神社のこちらの鳥居くぐって上っていくルートです。

この鳥居の先には階段が続いています。

この階段が一番しんどいかも(^^;)
ルートはこんな感じ

このしんどい階段を上り切って

石巻神社の最後の鳥居の手前に石巻山山頂へ向かう登山道が続きます。

登山道が整備されているのはうれしいのですが、この良く分からない階段はいかがなものかと(笑)

もはや階段の体をなしておらずただのトレーニングハードルです(笑)
でも上のようなのは一部でこういう自然に近い状態のルートが多いので良い感じです。

さらに進んで行くと山頂へ向かうルートと別のルートに分かれるのですがこちらは通行止めになっていますが、道の先に石垣が見えます。

何だろうと思っていたらこちらに解が。

石巻山城址があるようです。
この辺りから岩が大きくごつごつし初めて少し登るのに気を遣うようになってきました。

進んで行くと小さな洞窟が現れます。

石巻の蛇穴だそうです奥行きが13mもあるそうで神の使いの大蛇が住んでいたとかいないとか。

でもこの辺りは石灰岩なのでもしかしたら山口の秋芳洞のように地下に大きな鍾乳洞があったら面白いに。
そして全国各地に存在するダイラダボッチ伝説がここにも

なんでもかんでも大きな力が働いてできてような地形はみんなダイダラボッチの仕業にされますね(笑)

どのあたりが足跡なんだろう・・・?本宮山のといい良く分からない足形だこと。
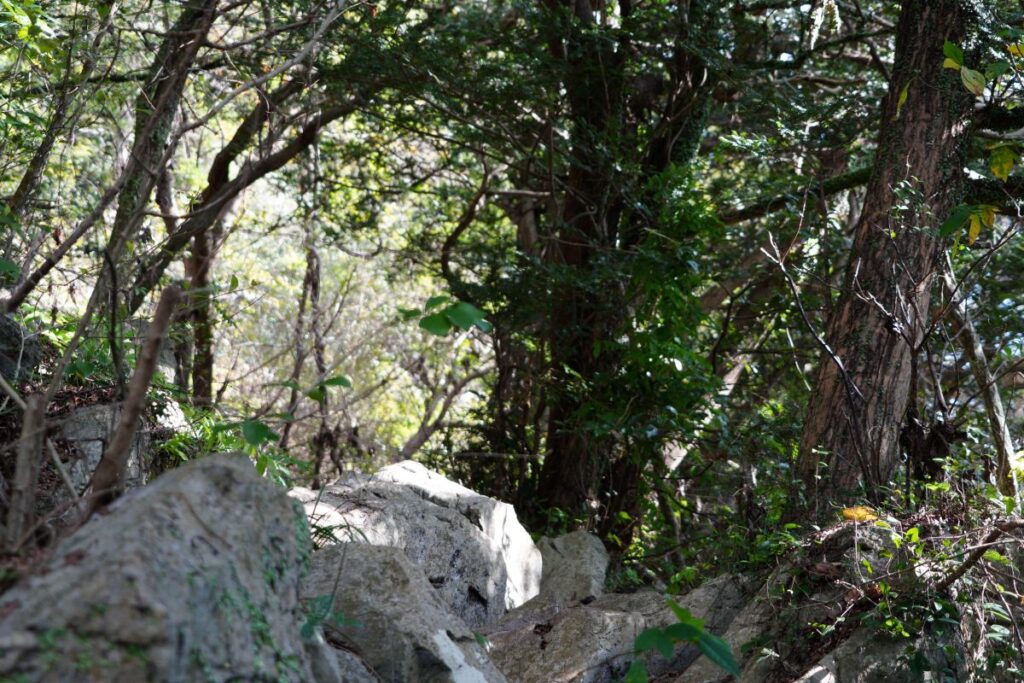
ごつごつした岩場が続きます。
そして滑りやすそうな岩場にはロープが掛けられていました。

この上には大天狗と小天狗の岩が

由来は良く分かりません(調べてもあまり出てこないから形からついたか?)
そして山頂が近づいてきた気配が見え隠れし始め

更に岩がごつごつしてくると・・・

突然現れるくさり場

ここが最後の難関らしいです。

更にその先はしっかりと金属製の階段が

こんなに急なのでこの階段が無かったら登るの厳しかったろうな。

そして光が漏れるこちらの最後の階段を上ると・・・

突如山頂の大パノラマが目の前に広がります♪

下に見えるのは三ツ口池。
昔の三ツ口池は江戸時代初期に当時の領主であった吉田藩藩主の命により、付近の原野を開墾する際の水源として造られたそうですが、今のは調整池として機能しているようです。
豊橋の街や渥美半島までよく見えました。

海も輝いてます。

高低差が本宮山の半分以下なので疲れはそれほどでもなかったですが、やっぱり登りは心拍数が上がりますね~。
心拍数が170以上になってスマートウォッチのアラートが出たりもしたけど、本宮山ほど長くはなかったかな。
これくらいの山ならそこまで心拍数を上げなくても登れるようになりたいものですな。
ということで、長くなりすぎたので後編に続く。
にほんブログ村



“愛知低山登山開始~石巻山前編” に対して1件のコメントがあります。